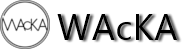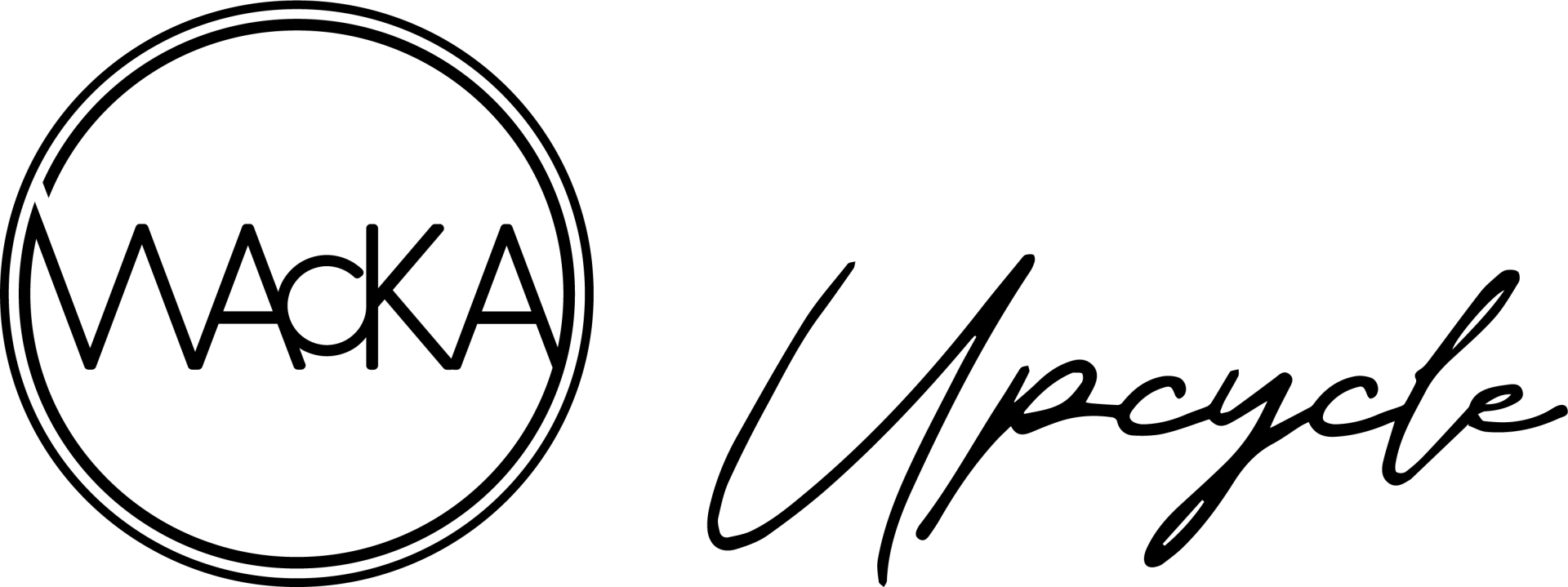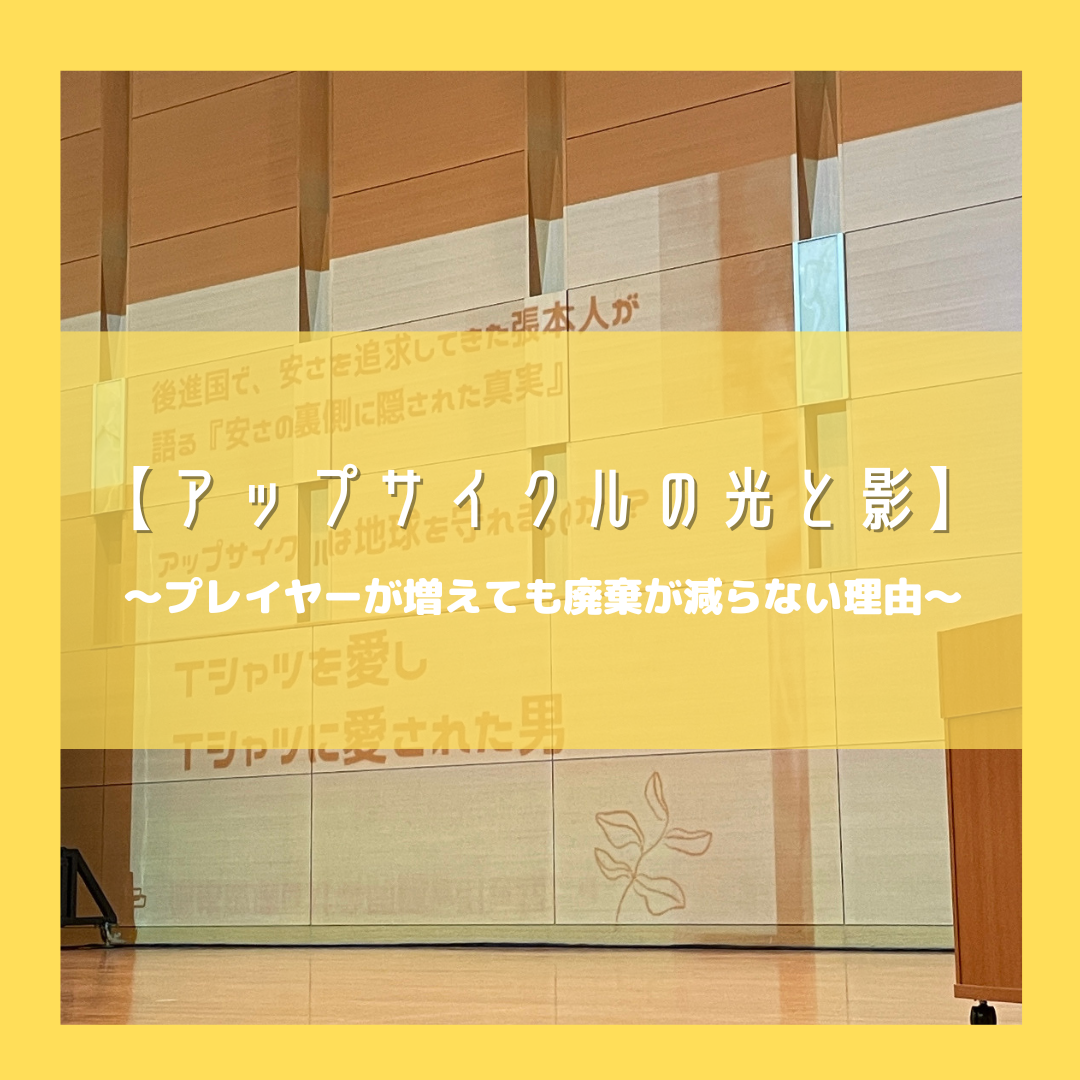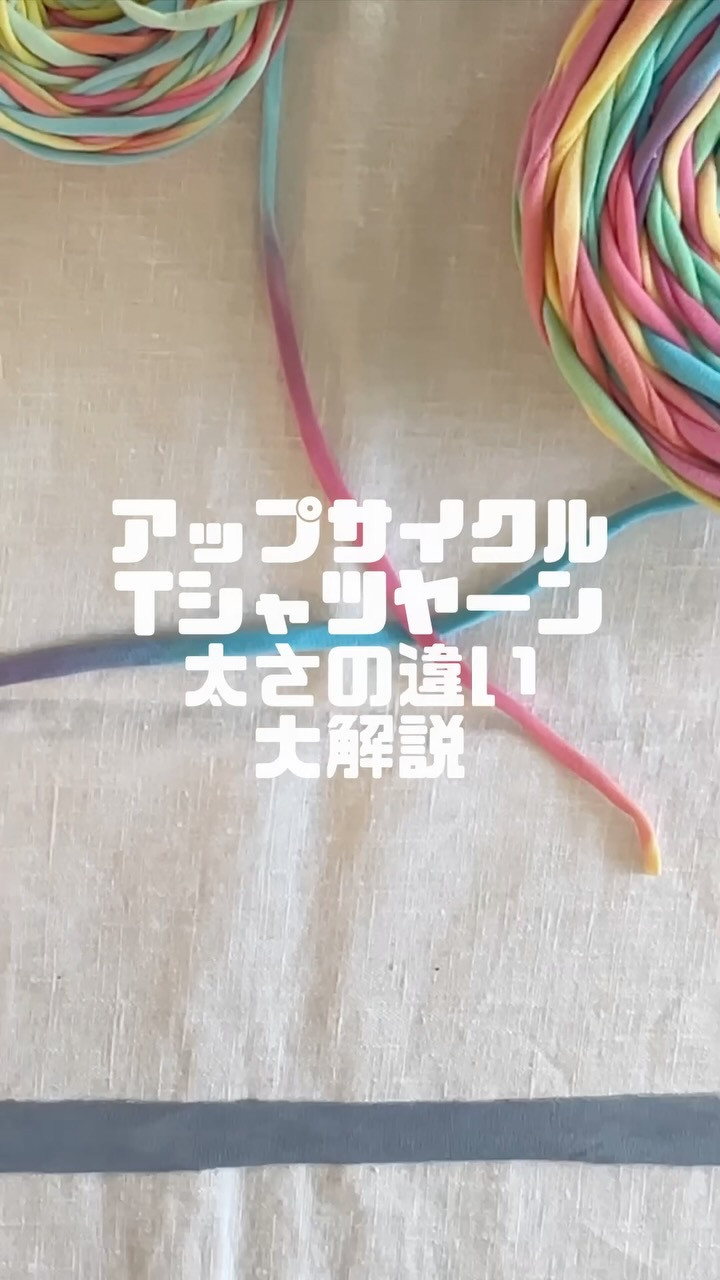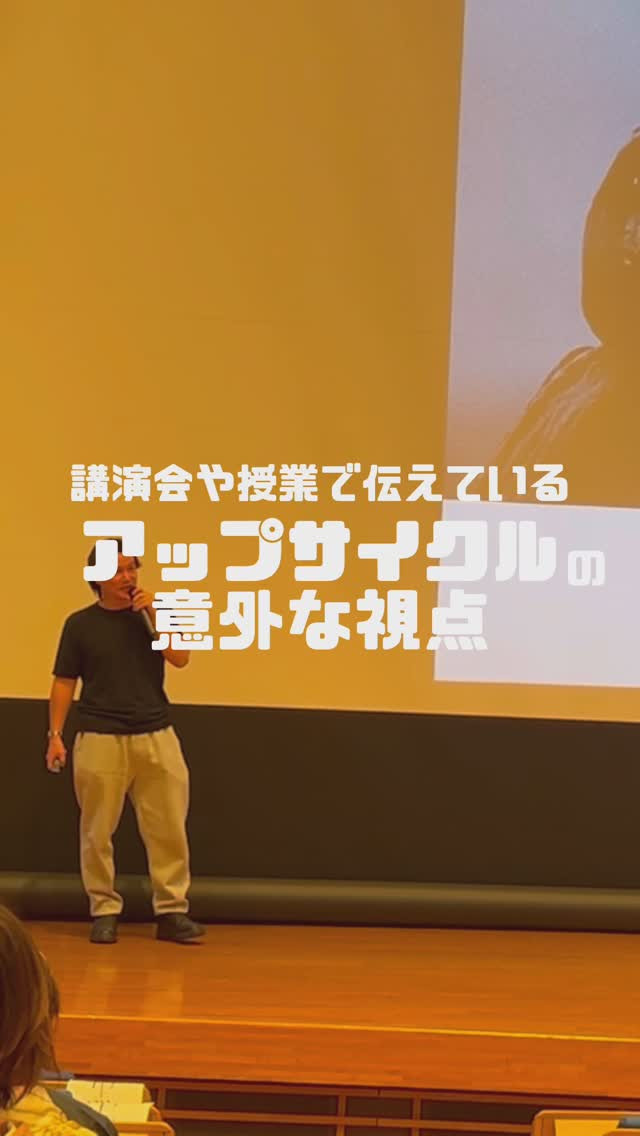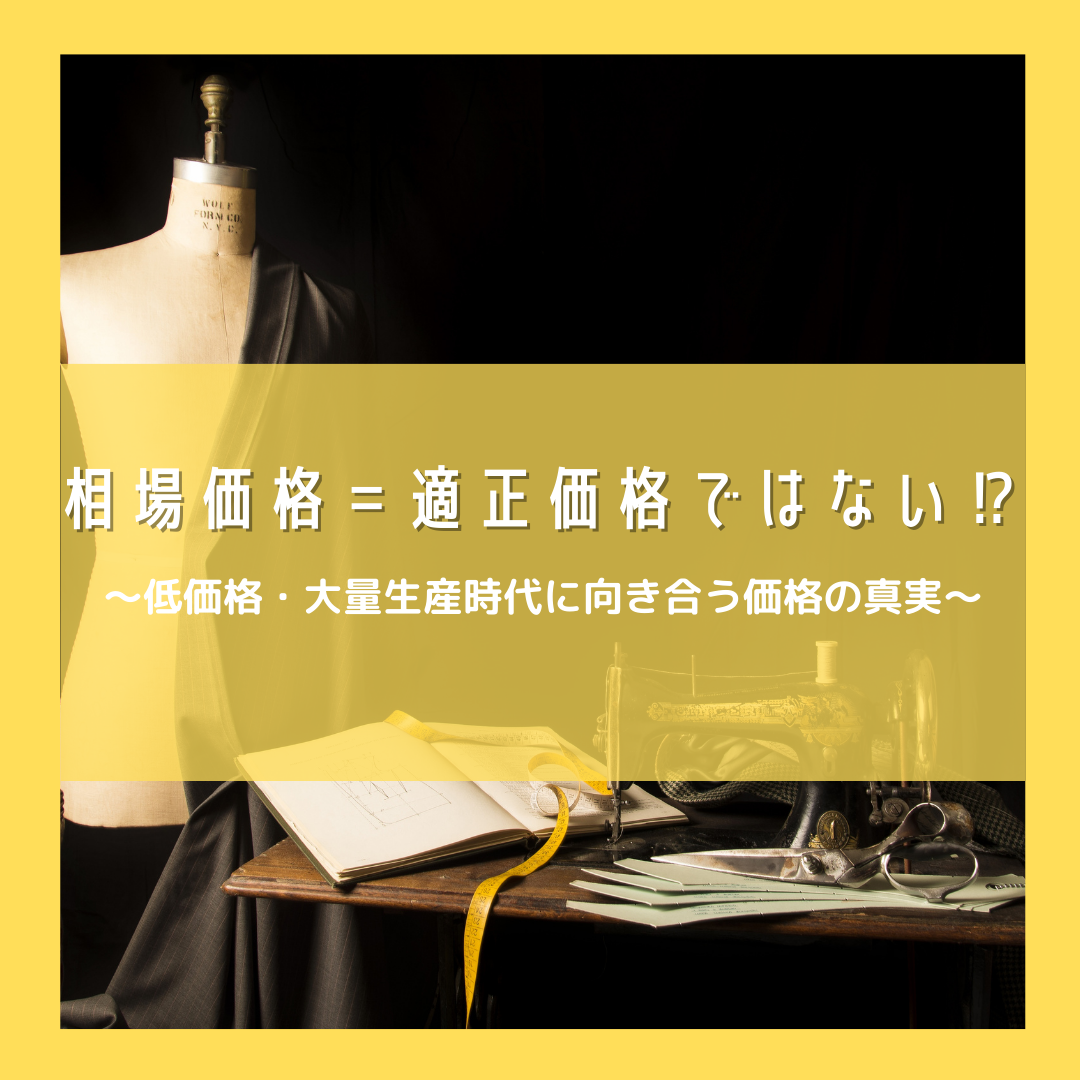【アップサイクルの光と影】~プレイヤーが増えても廃棄が減らない理由~
2025/01/27
【アップサイクルの光と影】
~プレイヤーが増えても廃棄が減らない理由~
ここ5年ほど、私が取り組んでいるアップサイクルも浸透し始め、その他にもサーキュラーエコノミーなど廃棄削減や再利用するという動きが活発になり始めました。
そうなると気になるのがその成果です。
残念ながら日本における衣料品の廃棄量は、近年一貫して高い水準に!
日本における衣料品の供給量は、近年やや減少傾向
• 2010年代前半:衣料品の供給量は増加傾向にありました。ファストファッションの台頭により、多くの新しい衣料品が市場に投入されていました。
• 2020年以降:コロナ禍や消費者の環境意識の高まりなどの影響で、供給量は減少傾向にあります。
2020年には新規供給量が約81.9万トン、2022年には約79.8万トンとわずかに減少しています。
ただし、供給量が減少しても廃棄量の割合は依然として高く、持続可能性を改善するための課題が残っています。
また
それにおそらく、供給力が減った理由は、環境意識の高まり以上に経済的な問題が多いのではないでしょうか?
野菜など食品価格などの高騰により、益々可処分所得が減少し、衣料品に掛けるコストがその分、削減されたことが大きな要因なような気がします。
廃棄量については
2020年には、国内で約81.9万トンの新規衣類が供給され、そのうち約78.7万トンが使用後に手放されました。この手放された衣類の約64.8%にあたる51.0万トンが廃棄され、残りはリユース(約19.6%)やリサイクル(約15.6%)に回されています。
2022年のデータでは、新規供給量は約79.8万トン、手放された衣類は約73.1万トンと若干の減少が見られます。
しかし、廃棄される割合は依然として高く、手放された衣類の約64.5%が廃棄されています。
これらのデータから、衣料品の大量生産・大量消費・大量廃棄の傾向が続いていることがわかります。
廃棄量が減らない場合の弊害
1. 環境負荷の増大
• 衣料品の廃棄は主に焼却や埋立処理により行われます。これにより、有害な温室効果ガス(CO₂やメタンなど)が発生し、地球温暖化が進行します。
• 化学繊維(ポリエステルなど)の焼却では、微細なプラスチック粒子や有害物質が放出されることもあります。
2. 資源の無駄遣い
• 衣料品の製造には多くの資源(石油、水、エネルギー)が消費されています。
廃棄が続くことで、これらの有限資源が無駄になり、持続可能性が損なわれます。
3. 土壌・水質汚染
• 埋立処理された衣料品から、有害な化学物質が流出し、土壌や地下水を汚染するリスクがあります。特に染料や加工剤が問題視されています。
4. 経済的損失
• 廃棄処理のコストが増加し、自治体や社会全体にとって経済的な負担が大きくなります。さらに、リサイクルや再利用による経済機会が失われます。
ではなぜ廃棄量は減らないのか?
廃棄量が減らない原因
1. ファストファッションの影響
• 安価で大量生産されるファストファッションは、消費者が短期間で衣類を捨てる行動を助長しています。流行が早く変わるため、頻繁に新しい商品が購入され、古いものが廃棄されます。
2. リサイクルの難しさ
• 混紡繊維や染色された衣料品はリサイクルが技術的に難しい場合があります。そのため、多くの衣料品が廃棄される状況が続いています。
3. 消費者の意識不足
• 衣料品の廃棄が環境に与える影響についての認識が不足しているため、使い捨ての消費行動が減りません。
4. リユース・リサイクルインフラの不足
• 衣料品を再利用したり、リサイクルしたりするためのシステムが十分に整備されていない地域が多いです。特に、リユース品の流通網やリサイクル技術の普及が遅れています。
5. ブランド側の責任不足
• 衣料品メーカーやブランドが製品の廃棄後のライフサイクルを考慮していない場合が多く、持続可能な製品設計が進んでいません。
6. 経済的な理由
• 低価格の商品を手にしていたことが、結果、低収入しか得れない状態になったことで、低価格で短期間で使いまわすという選択肢しか選べなくなった。
改善に向けたアプローチ
• 消費者に対する教育キャンペーンや、衣料品廃棄に対する規制の導入
• メーカーがリサイクルしやすい素材を使用したり、回収システムを導入する「拡大生産者責任」を強化
• 持続可能なファッション(サステナブルファッション)の普及や、リユースを促進するためのプラットフォーム整備
廃棄量を減らすには、消費者・企業・行政が一体となった取り組みが必要
私たちアップサイクルを進める上で大切な事は
表面解決だけではなく、根本解決をしなければなりません。
例えば、宿題をしない子供に無理やり宿題をさせても、それは一時的な表面解決であり、根本的な学力向上や勉強の必要性や楽しさを理解している事にはならず、また翌日には、無理やり宿題をさせるという表面解決が繰り返される。
他にも例えば、ダイエットをしようとした時、一時的に食事制限したり、一時的にスポーツをしたりするのが、表面的な解決、結局、すぐリバウンドしますよね!
食事や生活習慣を見直し、健康的で継続的な改善を行うのが、根本解決にあたります。
アップサイクルでも同じです。
アップサイクルは、
『廃棄される運命にあるものに新しい魂を吹き込み、元の価値より高めて使用する』
と説明されることが多いです。
だけど
これは目的ではなく、手段です。
ではその目的とは何でしょうか?
【廃棄量の削減】
私たちアップサイクルに関わる人間が、もっとも忘れてはいけないことは、廃棄の削減を目指すことです。
そして一時的には、アップサイクルを広める必要がありますが、目指すべきゴールはアップサイクルする必要のない社会にすることです。
以前の企業様との取り組みは、
『廃棄する予定のものを提供下さる』までが、作る責任とされていましたが、最近では、『自分たちで形を変えてでも売り切るというところまでが責任』と責任の幅も変わってきました。
このような変化が加速する事も大事ですし、私たちアップサイクルに関わる人間が、企業にも、消費者にも、『作る責任・つかう責任』を訴えてこそ、目的達成に近づきます。
元々、ビジネスも人のお困りごとや生活を便利にすることで、存在し、その役割を終えると業態を変化したり、やり方を変えたりすることの企業が生き残ります。
アップサイクルも時代の変化に対応しながら、根本解決を目指し、役割が終われば、また違う社会活動に取り組めれば良いのではないでしょうか?
~@wacka_upcycle~
WAcKAでは、バングラデシュやベトナムでの駐在体験や繊維産業や社会福祉と関わりながら、感じたことを発信しています。
メディアでは報道されないリアルな現実を、できるだけ忖度なく発信しています。
共感や理解を得れなくても、知られざる真実を伝えたいです。
インスタアカウント:@wacka_upcycle
電子書籍も販売中 ご購入はこちらより
----------------------------------------------------------------------
WAcKA
〒276-0026
千葉県八千代市下市場1-4-8
電話番号 :
080-4294-1713
----------------------------------------------------------------------