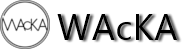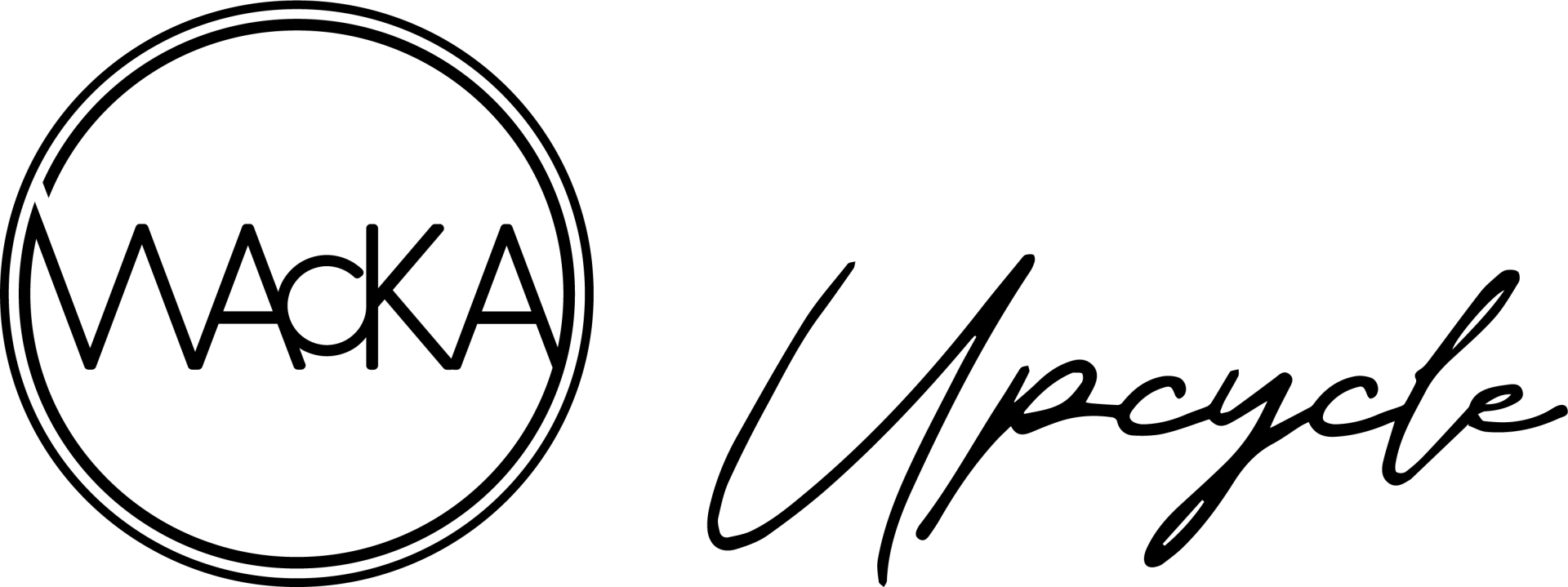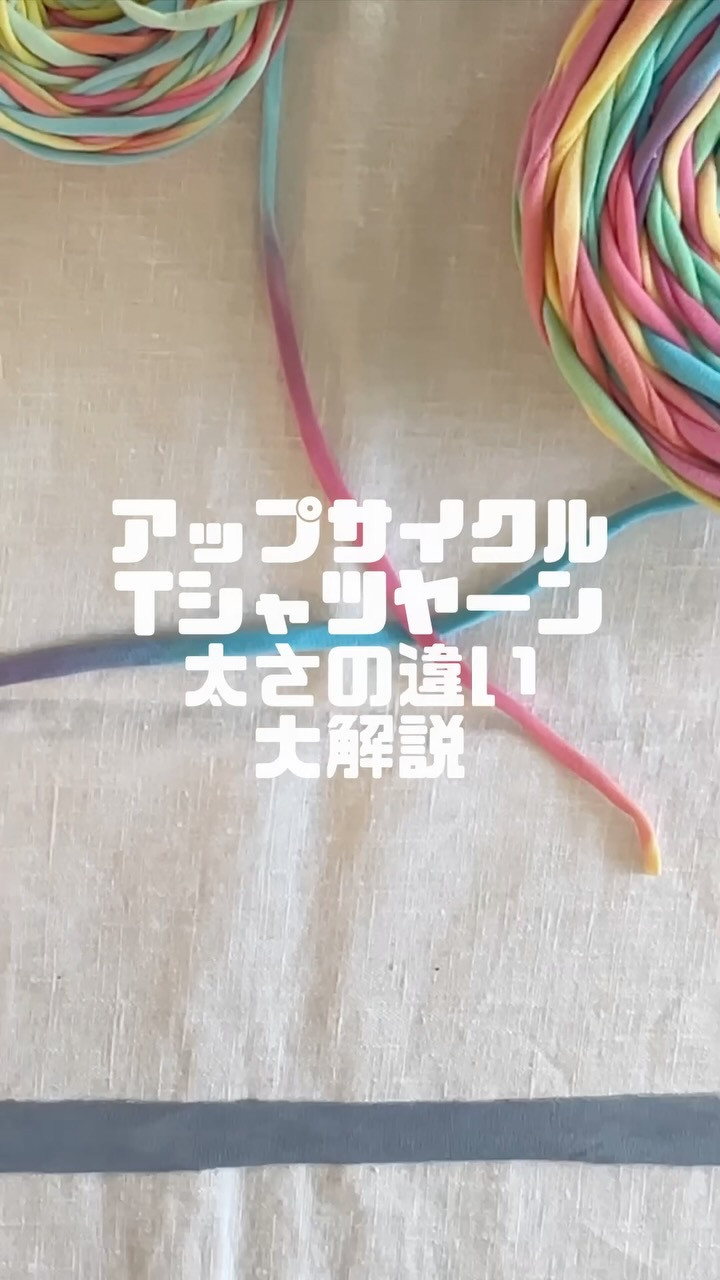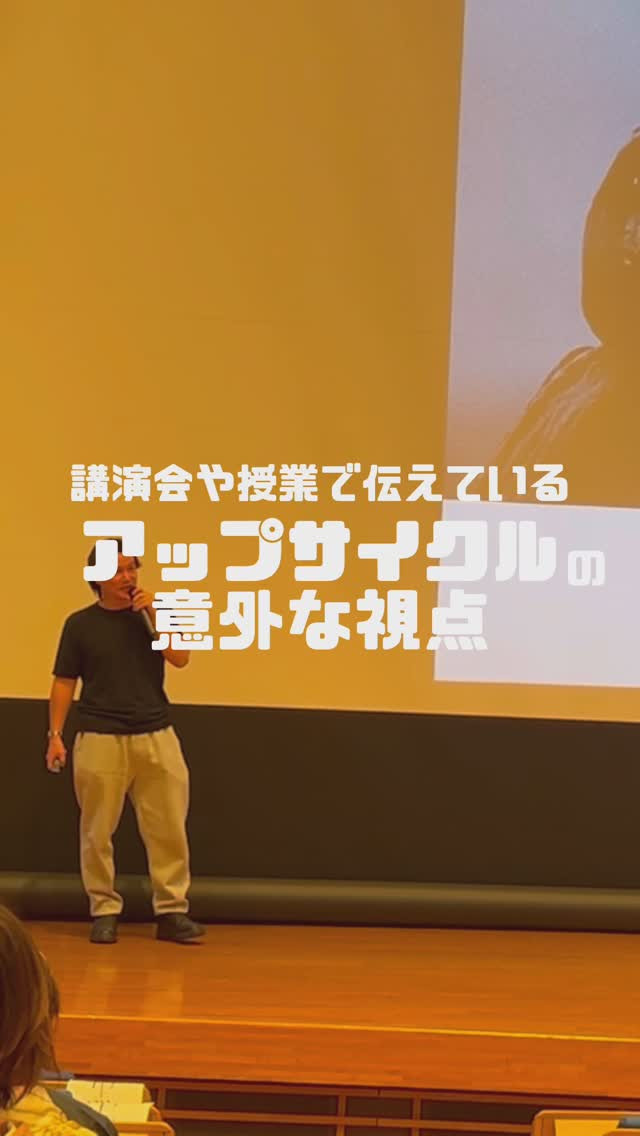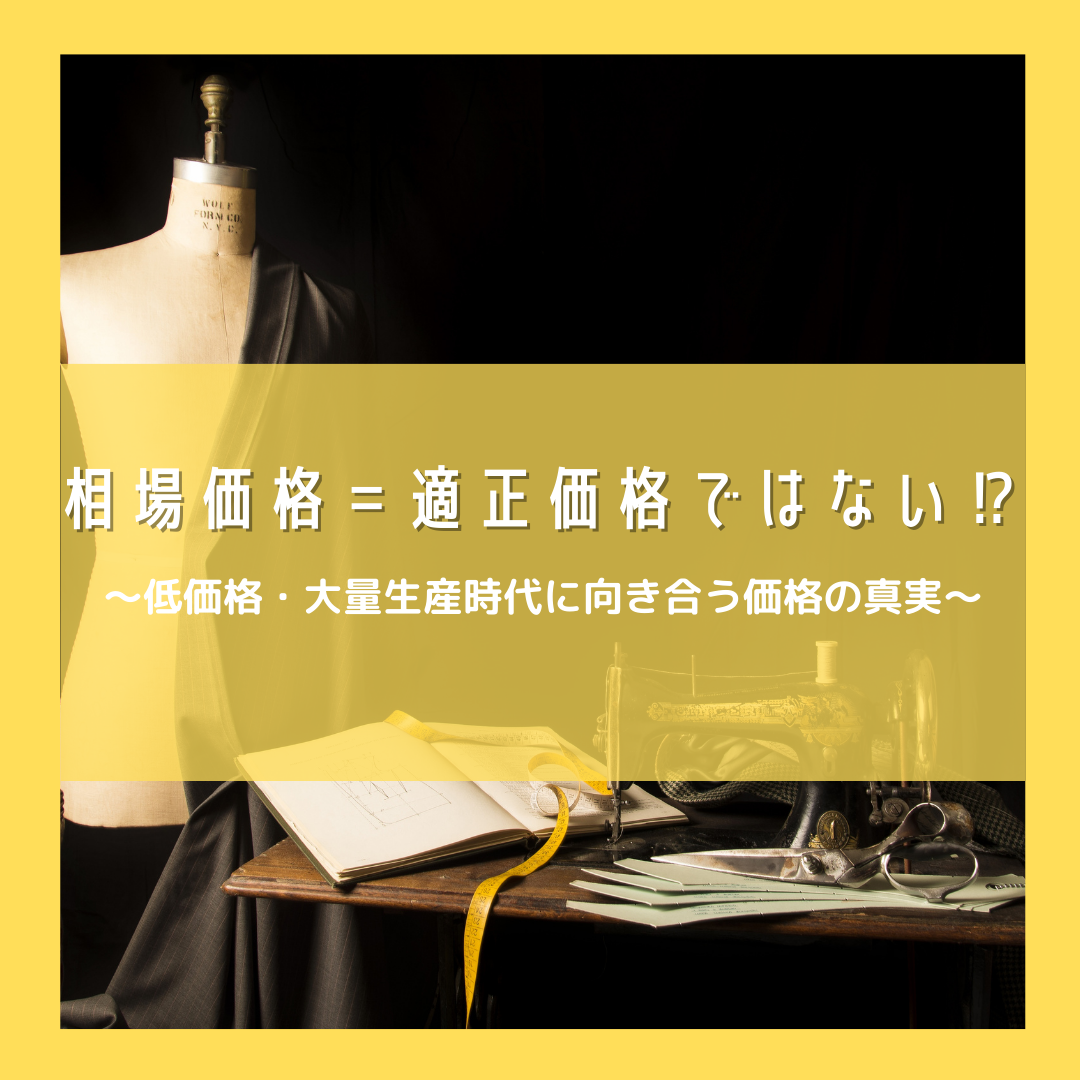食品を寄付すると損をする?って知ってますか?
2025/01/29
食品を寄付すると損をする?って知ってますか?
皆さん信じられないかもしれませんが、明日の食べ物にも困っているという方が、日本の中にもたくさんいます。
朝食支援やフードバンク事業に携わっていた時期があり、本当に切実に困っている方がいるのを実感しました。
日本だと『そんなの自己責任でしょ』と思われるかもしれませんが、そろそろ社会問題として認識しないと手遅れになるかもしれません。
数値でみる日本の貧困の現状
• 相対的貧困率(2018年データ):15.4%(約6.4人に
• 子どもの貧困率:13.5%(約7人に1人が貧困)
• ひとり親世帯の貧困率:48.1%(約2人に1人が貧困)
• 生活保護受給率:約1.6%(受給資格があっても利用していな
日本は先進国でありながら、「見えにくい貧困」が広がっ
明日の食べ物にも困る人々
•子ども:給食が唯一のまともな食事で、長期休み中に栄養が不足
•高齢者:年金だけでは生活が成り立たず、食費を削る人が多い。
• シングル:収入が低く、子どもと共
•非正規労働者:最低賃金が低く、月収10万円以下で食費を削ら
一方で、食品はあり余り、食品ロスやフードロスとして全く真逆の課題が存在します。
両方の課題をうまく結びつければ、2つの課題が一気に解決できそうに思いますが...
実はそこには日本独自の法律や文化背景が大きく起因しています。
欧米と日本の食品寄付に関する税制の違いを比較すると、その課題感が見えてきます。
欧米では
アメリカ(米国)
「寄付控除(Charitable Contribution Deduction)」
・企業が食品を寄付すると、市場価格の最大2倍の金額を損金(経
・企業は食品を寄付することで、税負担を軽減できるため、廃棄よ
「善意の食品寄付法(Good Samaritan Food Donation Act)」
・企業が善意で食品を寄付し、万が一健康被害が発生しても、重大
フランス
食品寄付を義務化(2016年法改正)
・スーパーなどの小売業者は、売れ残り食品を廃棄せず、慈善団体
寄付の税額控除
・企業が寄付した食品の価値の**最大60%**
イギリス(英国)
「Gift Aid(ギフト・エイド)」
・企業が慈善団体に食品を寄付すると、税制優遇が受けられる。
・企業にとって寄付のコストが軽減されるため、フードバンクなど
日本の食品寄付に関する税制
食品寄付に対する控除がほぼない
・日本では食品を寄付しても、企業の税負担を軽減する明確な税制
一方で、売れ残った食品を廃棄すれば**「損金処理」**とし
結果的に廃棄のほうが企業にとって得になりやすい。
法人税法の「寄付金」として扱われる
・日本では食品を寄付すると「寄付金」とみなされ、一定の控除枠
課税対象になってしまう。
そのため、大量の食品を寄付しようとすると、企業に追加の税負
食品廃棄への規制は緩い
・日本では食品ロス削減のための努力義務はあるものの、フランス
欧米では食品寄付を促すための税制優遇が手厚く、企業が積極的
日本では寄付に対する税制優遇が少なく、むしろ寄付すると企業
改善策として、日本でも「寄付金の税額控除強化」や「フードバ
今後、日本でも欧米のような仕組みを取り入れれば、食品ロス削減
自己の責任としてできる事もあるでしょうが、
日本の自己責任論では解決できない社会課題の多くは、構造的な要
例えば、貧困、労働環境の悪化、
しかし、
日本ではしばしば「自己責任」が強調され、政治や企業の
例えば、非正規雇用の拡大や低賃金問
同様に、教育や医療の格差、少子化
政治責任として求められるのは、
1. 社会保障や労働政策の整備による格差是正
2. 公共サービスの充実と負担の適正化
3. 長時間労働や低賃金問題への規制強化
自己責任論を前提にすると、これらの問題は放置され、結果的に社
政治の責任を明確にし、
~@wacka_upcycle~
WAcKAでは、バングラデシュやベトナムでの駐在体験や繊維産業や社会福祉と関わりながら、感じたことを発信しています。
メディアでは報道されないリアルな現実を、できるだけ忖度なく発信しています。
共感や理解を得れなくても、知られざる真実を伝えたいです。
インスタアカウント:@wacka_upcycle
電子書籍も販売中 ご購入はこちらより
----------------------------------------------------------------------
WAcKA
〒276-0026
千葉県八千代市下市場1-4-8
電話番号 :
080-4294-1713
----------------------------------------------------------------------